 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皆さんこんにちは。
令和6年10月の建築家コラムをお届けします。 まだ暑い日もありますが、朝晩は冷え込むようになってきましたので、皆様におかれましては体調管理に十分気をつけてお過ごしください。 さて、建築家コラム43回目のゲストは「相坂 研介(あいさか けんすけ)」さんです。 相坂さんは東京大学工学部建築学科を卒業後、安藤忠雄建築研究所に勤務され、美術館や公共施設のプロジェクトを経験し、2003年相坂研介設計アトリエを設立されました。独立後も、住宅や家具、ビルや保育園まで幅広く設計してご活躍されています。 今回、相坂さんからどんな「床」にまつわるお話が聞けるのかとても楽しみです。 それでは相坂さんのコラムをお楽しみください。 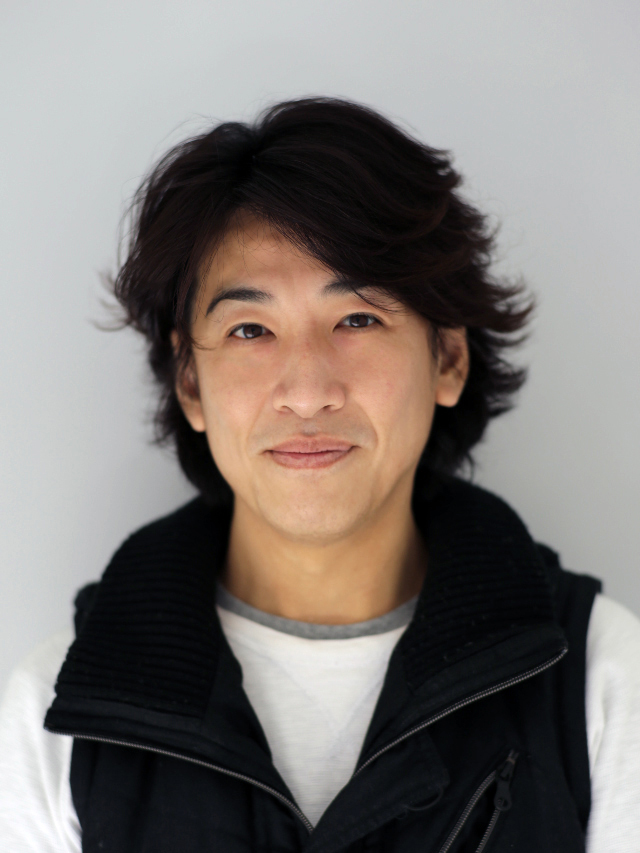 相坂 研介(あいさか けんすけ) / 建築家
相坂 研介(あいさか けんすけ) / 建築家1973年 東京都生まれ。1996年 東京大学工学部建築学科卒業〜2002年 安藤忠雄建築研究所 勤務を経て、2003年 相坂研介設計アトリエ設立。法政大学、東洋大学講師。 日本建築学会、東京建築士会、建築士事務所協会 正会員。日本建築家協会 登録建築家。 (主な作品) 『東立石保育園』『あまねの杜保育園』 『Building of Music』『丸栄慶運館』『藤沢の住宅』 (主な受賞) UIA Friendly & Inclusive Spaces Awards、 Architecture Asia Award、 日事連建築賞 国土交通大臣賞、 東京建築賞 東京都知事賞、こども環境学会デザイン賞、 JIA東北建築大賞建築賞、PHASE FREE AWARD、 これからの建築士賞、JIA環境建築賞、JIA優秀建築選、 グッドデザイン賞、キッズデザイン賞 他 国内外で受賞 床が動く/床を動く −建築の自由度と回遊性― 私は、長い寿命を授かる建築を、人々がなるべく思い通りに、飽きずに使えるようにしたいと考え、設計を続けている。特にモノの側が動く性能を「自由度」、ヒトの側が動きたくなるポテンシャルを「回遊性」と呼び、双方を追求している。 <床が動く> 建築の密度を表す「容積率」という言葉があるが、実際は床面積/敷地面積という面積比が使われているのは興味深い。床の広さと空間の大きさが比例関係にあり、「床がなければそこに容積がない」かのようだが、実際は違うはずである。 同じ床面積でも、吹抜けの大きな気積は豊かな開放感を与えるし、壁で仕切られてばかりでは、その時その中にいる人が使える真の意味の「容積率」は大変低い。そんなことを考えながら、「床が現れたり消えたりする住宅」を作った。 (写真1.2階客室の床が跳ね上がる可動床) Photo ©MitsuoMatsuoka
駐停車スペースに敷地の多くを奪われる車好きの方の住宅で、利用に応じて床面積を増減させつつ「真の容積率」を最大に保ち続けるのが目的で、2階の床=1階の天井が2つ折りに跳ね上がる“可動床”を発明した。客がいなければ全く不要な客室の容積を、普段は階下のリビングに加えることが出来るため、未使用室を隠すだけの可動間仕切とも異なり、床の広さに関わらず、使っている容積は最大に保てる。“可動床”は、法的な容積率にはもちろん「床が有る」ものとして算入し、構造的には単なる荷重とし、水平耐力を負担できる“床は無い”ものとして、それぞれ不利側で確認申請を通した。
(図1.藤沢の住宅)(図2.可動床詳細図)
<床を動く> 一方、建築自体が動かずとも、ヒトは自らが動き、視点を変えていくことで、趣を感じてきた。暗い茂みから明るい州浜まで巡る池泉回遊式庭園はかつての大名の楽しみであったし、切り取られた風景が刻々と変わるシークエンスを感じながら内外歩いていく空間体験は、現代においても建築を飽きずに堪能する楽しみ方の大きな一つであろう。 私が保育園や幼稚園などを依頼された際には、行き止まりのない立体回遊動線の道中に、日向や日陰による明暗、階段やスロープといった上り方・下り方、ブリッジや滑り台など移動の種類、芝や土や川底の石などの踏み心地など、さまざまな空間体験を仕込むのだが、これらは全て連続した床であり、動きまわりたくなる床を考えているともいえる。 (写真2.多彩な床で様々な空間体験ができる「あまねの杜保育園」) Photo ©Shigeo Ogawa
子どもたちがのびのびと飽きずに移動できる、行き止まりなく複数の選択性のある動線計画は、大人の維持管理にも有効であるうえに、誰もが逃げやすく腰掛けやすい床とすることで、河川の氾濫や地震などの災害時には一時避難場所として地域防災にも寄与できるため、広義の「回遊性」は、「自由度」と並ぶもう一つの主要テーマと考えている。
(写真3. 河川の氾濫時には地域の避難所となる「東立石保育園」) Photo ©Shigeo Ogawa
今回の執筆で、自らが追求してきたテーマ、「モノが動く自由度」にも「ヒトが動ける回遊性」にも、モノとヒトが必ず接する面=「床」の存在が大きいことに、あらためて気づくことができた。両者の境界面が「床」である根拠には、“重力”の存在が大きいのだろう。床を動かせる性能は、建築における最大の自由度の獲得だと考えていたが、今後はさらに進展するであろう技術の力を借り、重力をも自由にする建築を考えてみたい。
相坂さん、ありがとうございました。 開閉する可動床のアイデアには驚きましたが、床が動く建築と床を動く建築、どちらも相坂さんが設計される建築の楽しさが伝わってきました。 いつか重力を自由にする建築も見てみたいと思います。 これからもますますのご活躍をお祈りしております。どうもありがとうございました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|















